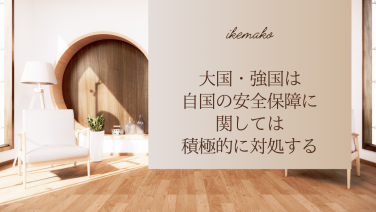 平和論
平和論 大国・強国は自国の安全保障に関しては積極的に対処する
一昨年2月24日から始まったロシアのウクライナへの侵攻にしろ、昨年10月7日ハマスによる攻撃に対してイスラエルが行っている掃討作戦にしろ、世の多数派の意見とは異なって、私は両国とも、自国の安全保障のための行動であると考えます。 前者に関して...
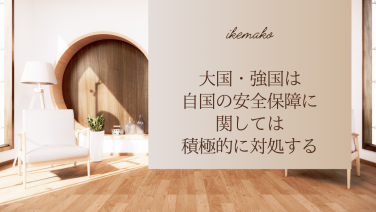 平和論
平和論  平和論
平和論  平和論
平和論  平和論
平和論